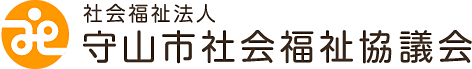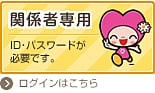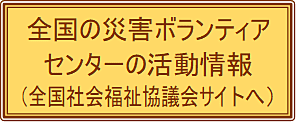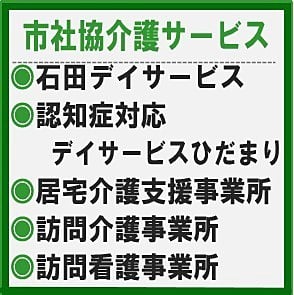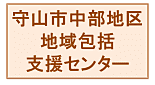守山市共同募金委員会(事務局:守山市社会福祉協議会)
〒524-0013滋賀県守山市下之郷三丁目2番5号
電話077-583-2923 FAX077-582-1615
目次
災害義援金情報
義援金情報はこちらから
共同募金って?
共同募金は、原則として、募金をした地域(都道府県)の地域福祉活動を支援するために使われます。
守山市で集まった募金のうち、滋賀県内の広域的な事業におよそ4割を、また守山市内の福祉活動の推進のために、およそ6割を活用します。
共同募金は、1947(昭和22)年に生まれ、70年以上の歴史があります。
「赤い羽根募金」は共同募金の愛称です。「赤い羽根」は、第2回目の1948(昭和23)年から、募金の印として使われて以降現在まで、共同募金のシンボルとして定着しています。
共同募金運動実績
テーマ型募金
テーマ型募金(子どもの育ち応援募金)

募集期間: 1月1日から3月31日まで
目標金額: 500,000円
いつも赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございます。守山市共同募金委員会では、赤い羽根共同募金を10月から12月に実施し、1月から3月までを地域の課題解決のための募金としてテーマを決めた課題解決型募金に取り組んでいます。
令和2年度からは、課題解決型募金として子どもの福祉課題の解決をめざした『子どもの育ち応援募金』を実施いたします。
子ども食堂の運営ボランティアや学校安全ボランティア、学習支援ボランティア、地域の子育てサロン運営など地域で子どもの育ちを支援する活動に取り組まれている人や団体を応援することを目的としています。
市内全域に本運動推進のため、ご協力いただきますようお願い申しあげます。
ご協力のお申し出は、
守山市社会福祉協議会まで
☎077-583-2923
令和6年1月から3月までの子どもの育ち応援募金実績報告と使い途

募金総額 : 591,289円
ご協力ありがとうございました。
いただいた募金は、
・飛び出しもりぴーの製作
・子育て応援フォーラムの実施
・子ども福祉委員活動
に活用します。
今後ともご協力をお願いします。
助成金を受ける
令和6年度 地域福祉活動助成事業
| 様式(申請書・請求書・報告書) ( 34KB ) | |
市内の福祉関係団体が行う活動に対して助成を行います。 助成金申請の手続きは、下記のとおりです。 ① 申請書に必要事項記入・押印後、資料を添えて(見積書など)提出 してください。 ② 決定通知書を発行いたしますので、請求書を提出してくださ い。 ③ 請求書に基づき、助成金(概算払い)を振込みいたします。 ④ 助成金を活用して事業が完了後、報告書を提出してください。 |
助成の周知事例について
| 助成事業の周知事例 ( 1816KB ) | |
赤い羽根共同募金の助成を受けた団体は、周知事例を参考に 地域の皆さまに「ありがとう」の気持ちをお伝えください。 1.「赤い羽根ありがとうシール」を購入品等に貼付願います。 ※助成決定通知書と同封してお渡ししていますが、足りない場 合は守山市共同募金委員会へお申し出ください。 2.貼付できないものについては、名入れ(印刷・刺繍等)を お願いします。 ※ロゴマーク等、周知事例からデータをご利用ください。 |